ランタンレッド
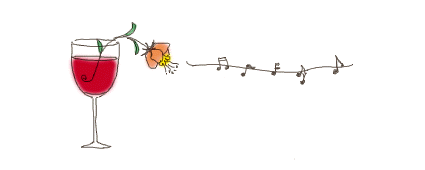
「松平のとっつぁんが、今夜はスナックすまいる付き合えってよ!」
近藤がうきうきと肩を弾ませて言い、土方は疲れの滲んだ声で答えた。
「……近藤さんだけ行っときゃいいんじゃねぇの?」
近藤はそんな土方の様子を気にもとめず、がしりと肩を組んで威勢よく笑う。まるで散歩に連れて行ってくれとねだってぶんぶん尻尾を振る若い犬のようだ。土方はうっとうしくて敵わない。
「何言ってんだよトシ! お前、お妙さんに会いたくねぇのかよ!」
「そう思ってんのは近藤さん以外にいねぇよ」
「とっつぁんの話によるとな、今日は特別に店を貸し切ってのパーティらしんだよ。きっと盛り上がるぞ!」
「だったら暇そうな隊士でも連れてってやればいいじゃねぇか」
「だったらなおのことお前も来いよ! お前がひとりで残業なんかしてたんじゃ、下の連中も心置きなく休めねぇだろ? な!?」
得体の知れない説得力のある笑顔を向けられ、土方は仕方なく折れた。
「あら、土方さん。こんばんは」
店に入って一番に土方を出迎えた女が誰か、気がつくのにしばらくかかった。絹糸の刺繍が施された豪華な着物は朱色を基調としているが派手すぎると言うことはなく不思議と落ち着いた雰囲気がして、完璧に結い上げた髪も化粧もどちらかといえばシンプルだ。だからこそ元の人相が分からないほど濃い化粧で武装した女の中で、その女は浮いていた。どちらかと言えば、小さなスナックのママと言った方が似合う。
「ようこそ、お待ちしてました」
「えーっと……?」
「私、です」
はいたずらが成功した子どものようにピースサインをして笑った。艶やかな紅を引いた唇が弓形にしなる。土方は狼狽えた。
「なんでお前がこんなとこにいんだよ?」
「言ったでしょう? 用事があるから今日はお仕事お休みしますって」
「いやそれは聞いたけどよ……」
「松平様にお誘いいただいたんです。たまには羽を伸ばしなさいって」
「その格好は?」
「松平様が貸してくださったんです。似合いますか?」
「……あぁ、まぁな」
「ちょっと迷いましたね」
「すぐ答えたっつーのっ」
「おぉ、なんだトシ。遅かったじゃねぇか」
の肩を抱きながら現れたのは松平だ。土方はとっさに居住まいを正したが、まだショック状態から抜け出せずにいて、あまりうまくはいかなかった。
「今日は無礼講だからな。楽しんで行けよ」
「とっつぁん、こいつを連れて来るならなんで俺に一言言わねぇんだよ?」
松平はすぱすぱと煙草を吹かせながら、にこやかに微笑んで隣に立っているを見下ろして首を傾げる。
「ちゃんを遊びに連れ出すのにお前の許可がいるのか?」
「そういう問題じゃねぇ」
「だったらなんの問題がある? いいじゃねぇか、今日は無礼講だと言ったろう。いつもお前らの世話焼いて大変なんだよ、ちゃんは。なぁ?」
「お気遣いいただいて、ありがとうございます」
「というわけで、ちゃんは俺と飲むから。お前も好みの女の子捕まえてよろしくやんなさいよ」
「ちょっと待てよおい……!」
土方が止める間もなく、松平はの肩を抱いたままさっさと店の中に消えてしまう。去り際、が松平の肩越しに意味ありげな視線を寄越したが、それはからかうようないたずらっぽい目線で、土方はイライラした。あのふたりは一体何がしたいのか、さっぱり分からなかった。
スナックすまいるで開かれたパーティは、松平片栗虎の誕生日パーティだった。
いい歳をしたおっさんがスナックで誕生日パーティを開くだなんて、土方はもの悲しさを感じずにはいられなかったが、店のありさまを見て納得した。常連客の誕生日というのは、店側にとって稼ぎ時なのだ。いつにも増して賑やかな店内はいつにも増してきらびやかな女達と酒と料理に溢れ、きらきらと輝くシャンパンタワーとシャンデリアに目がちかちかした。
松平は店の真ん中の一番いい席でを隣にはべらせていて、近藤もその隣の席で必死にお妙を口説いている。店内には松平と懇意にしている幕府の重鎮やそこまで親しい関係ではないがこれを機に松平に気に入られようと躍起になっている幕閣がいて、なるほど、ここに顔を出すことの意味はかなり大きいらしい。
松平の隣、飾りのように腰を落ち着けているは、何がそんなに楽しいのか微笑みを絶やさず、にこにこと松平の話に相槌を打っている。同じテーブルを囲んでいる警察局のトップの何某(顔は知っているが名前を忘れた)が、を気に入ったのか隣に陣取って身を乗り出し、膝に手を置いたりしているものだから、土方は気が気ではなかった。土方の隣に座った若い女が甲高い声で何か話していたが全く耳に入ってこずただただ鬱陶しいばかりだ。
もしが真選組の家政婦だと知られたら、その立場につけ込んで情報を得ようとするかもしれない。真選組は幕府お抱えの機関とはいえ、所詮は田舎の野良武士の集まりだ。存在自体を面白がっていない連中はいくらでもいる。そういうきな臭い連中にを関わらせるのは嫌だった。はあくまでも一介の家政婦であって、幕府のごたごたや面倒臭いあれこれには一切関わって欲しくなかった。そうなったら最後、どんな場所に行きつくのかは土方にも分からない。
それが嫌だから土方はこれまで必死でを真選組の仕事や幕府との面倒臭い人間関係には首を突っ込ませないで来たというのに、どうして松平は余計な気を回すのだろう。
そもそも松平の誕生日パーティーとはいえ、スナックに女を連れてきて羽を伸ばせという神経が土方には理解できなかったし、それを素直に受け入れているの考えていることも分からない。松平から命じられれば断ることはできないと分かってはいるが、だからこそ、頭の禿げ上がった男の相手をして、あんな風ににこにこと笑っているなんて、何かの罰ゲームとしか土方には思えなかった。
何が羽を伸ばせ、だ。俺たちがを屯所でさんざんこき使っているみたいな言い方をしやがって、確かにあれだけの隊士が暮らす屯所の家事をほとんどひとりで切り盛りして休みもないのだからあながち間違ってもいないが、だからといってこういう場所に連れてくればそれで満足してもらえるものなのだろうか。
手洗いに立った時に近藤にこのことを話してみたら、「心配しすぎだ!」と豪快に笑い飛ばされてしまった。相談する相手を間違えたと思った。何せ近藤は酒とお妙に酔って、財布の紐があってないような状態になっている。もう少し良識を持った人間はいないものだろうか。
土方がそんなことを考えて、絶望的な気分で酒をあおったとき、テーブルの向こうからが土方を見てかすかに笑った。土方はそれだけのことにどぎまぎして慌てて俯いて視線をそらす。まだ経験の浅い若い女の作った焼酎の水割りは味が分からないほど薄い。
と、はひとりで席を立ち、土方のそばを通り過ぎる瞬間に流し目を寄こす。それを合図と思って、土方も少し遅れて席を立った。店の奥にある手洗いのさらにその奥の扉の前で、が土方を手招きしたので誘われるまま足を踏み入れたら、そこは酒の在庫が積み重なっているバックヤードだった。
「いいのか? こんなとこに逃げてきて」
土方が煙草の煙に乗せて嫌味な声で言うと、は壁にもたれ掛かりながらくすくすと笑った。
「土方さんがあんまりつまらなさそうな顔してるんですもの。気になっちゃって」
「こういうところは性に合わねぇんだよ」
「あら、あんなに若くてかわいい子を隣にはべらせてるくせに」
「そうか?」
隣に座った女の顔をとっさに思い出せなくて、土方ははっとした。隣なんか一度も顧みず、遠くのテーブルに座るのことばかり見ていたのだ。たぶん、はそれを見抜いているのだろう、だからこんなところへ土方を誘ったのだ。
「俺はひとりで飲むのが好きなんだよ」
苦し紛れの言い訳をが信じたかどうかは分からなかったが、は形ばかりうんうんと大きく頷いた。
「それじゃ、つまらないのも仕方がないですね」
酒に火照った頬、耳の先や首筋までほんのりと赤い。着物の朱色と相まって、目を離せなくなるような艶っぽさがある。こんなを、あのテーブルに帰したくない。土方は強い気持ちで思う。
「……気分が悪い」
「あら、悪酔いしました? 大丈夫ですか?」
「大丈夫じゃねぇから、休憩付き合ってくんない?」
「いいですよ、もちろん」
が手荷物を取ってくるのを待って、ふたりで勝手口から外に出る。表通りは人でごった返していたから暗い裏道を気の赴くまま、ふたり手を繋いで歩いた。どちらから繋いだのか、きっかけはなんだったのかは分からない。いつの間にか自然にそうしていて、それをおかしなこととは思わなかった。
看板に赤い提灯が飾られたホテルが目に留まったので、目を合わせるだけの合図をして門をくぐる。適当にボタンを押して選んだ部屋についてみれば、そこは異国の雰囲気を模した洋室だった。柱と天井の梁以外、壁も天井もまるで血しぶきを浴びたように真っ赤な朱色だ。
「わぁ。真っ赤ですねぇ」
間延びした声では言い、くるりと回って部屋を見渡す。足元が少しふらついて転びかけ、それだけのことがおかしいらしくひとりで笑っている。こんなにふわふわと浮き足立ったを見るのは初めてで、土方は珍しいものを見た優越感で胸がざわついた。
「ずいぶん酔ってるな。相当飲んだろ?」
土方はテーブルの上の灰皿を引き寄せ、ソファに腰を下ろしてから煙草に火を着けた。
「あんまり強くないので、ひかえめにするつもりだったんですけど、松平様に進められると断れなくて」
「大丈夫か?」
「悪酔いしたって言ったのは土方さんですよ。そっちこそ」
「ちょっと外の空気吸ったらましになった」
「そうですか、良かった」
「お前は水でも飲んで落ち着けよ」
部屋に入る前に自動販売機で買っておいた水を、は舐めるようにほんの少しだけ口に含む。そしてベッドの縁に腰掛けると、楽しそうに含み笑いをしながら土方を見た。その視線が気まずくて、土方はおちおち煙草を味わう気にもなれない。
本当に、ずいぶん酔っ払ってしまっているらしい。もしかすると、明日になれば今日のできごとなどすっかり忘れてしまっているのではないだろうか。こんな状態のを抱いたとしても、それを覚えていてもらえないというのはなんだかものすごく虚しいことのように思える。
「先にお風呂使いますか?」
「いや、俺は……」
どうしたものかと迷って口籠っている土方を尻目に、はひとり、枕を抱えてベッドに倒れ込んだ。
「お前、本当に大丈夫か?」
「ふふふっ、だいじょうぶです。ぜんぜん、へいきです」
舌が回らないのか、子どものように舌ったらずにそう言い、はベッドの上から片手を伸ばしてきた。赤い部屋の真ん中で、真っ赤な顔をして赤い指先を伸ばしてくるの、誘うように潤んだ瞳。
土方は煙草の火を消して立ち上がると、ベッドの縁に腰掛けての髪を撫でた。は体を起こすと、甘えるように土方の膝の上に頭を乗せる。
「お前がこんなんなってんの見るのは初めてだ」
土方はの首筋に手を入れて頬を撫でてやる。
「幻滅しました?」
は頬を撫でる土方の手に自分の手を絡ませ、冗談めかしてそう言った。そんなわけはないと分かっていて、わざわざからかっていると土方にも分かる。けれどは酔っているので、仕方がなくその冗談に付き合ってみることにする。
「そうだな。こんなに酒にだらしのねぇ女だとは思わなかった」
意外なほど穏やかで優しい声が出て、土方は自分のことながら驚いた。言っていることと声色が真逆だ。もそれを感じ取ったらしく、土方を見上げて満足げに笑っている。
「あーあ、土方さんに嫌われちゃった。悲しい」
「安心しろよ。俺よりいい男なんて世の中にたくさんいるだろ」
「例えば?」
「それは自分で考えろよ」
「失恋したばっかりでそれは無理です」
「だったら明日目が覚めたら考えな」
「そうですね、そうします」
こうして意味もなく交わす言葉も、明日の朝、目を覚ましたら全て忘れてしまうだろうか。なんだかもったいないような気がした。馬鹿みたいに真っ赤な部屋、血しぶきに汚れたような場所で交わした戯言が、夢の中のできごとのようになかったことになってしまうのは惜しかった。が忘れてしまったとしても、自分だけはちゃんと覚えておこうと土方は思う。
「風呂入るか?」
「土方さん、お先にどうぞ」
「俺は後でいいよ」
「どうして?」
「お前ひとりで放っといたら先に寝ちまいそうだ」
「寝ませんよ」
「いや絶対寝る。風呂入って目ぇ覚まして来い」
「大丈夫ですって」
「もし先に寝やがったらただじゃおかねぇぞ」
「そこまで言わなくても……。何なんですか一体?」
「お前が寝ちまったら俺ひとりでどうすりゃいいんだよ」
急にが黙り込んだので、どうかしたかと思って見下ろすと、は笑っていた。一体何がツボに入ってしまったのか、まるで痙攣でも起こしたように肩を震わせているので、土方は不安になっての顔を覗き込む。
「おい、どうした? 大丈夫か?」
「えぇ、はい。だいじょぶです。ふふっ」
「何だよ?」
は涙が浮くほど笑った顔で土方を見上げると、土方の唇に人差し指を押し当ててうっとりと呟いた。
「土方さんってば、かわいい」
「かわいくねぇよ」
言葉尻に被さる勢いで土方は否定して、いつまでも笑い続けるの唇を指で塞いだ。
いつだったか、何かの折にお登勢さんと話をしていたことで、なんとなく覚えている言葉がある。
「男のために化粧をしているようじゃ、まだまだお子様」
その言葉の本当の意味を、今日ほど身にしみて感じたことはない。
今日のおめかしは、誰のためでもなく、私のためだけのものだった。綺麗な着物を着て、美しい髪飾りで着飾って、完璧なメイクをして、いろんな人にちやほやしてもらって、とてもとても楽しかった。気分がよかった。まるで自分じゃないみたいだった。
それに何より、大好きな人の視線をひとり占めにできた。あんなにかわいくて若い女の子がすぐそばで色気を振りまいているというのに、土方さんは一度もその子に目もくれなかった。じっと私だけを見ていてくれた、こんなに気持ちのいい思いをするのは生まれて初めてだった。おかげでお酒もすすんだ。
あんまり楽しすぎていろんなことを忘れてしまった気がするけれど、心から楽しかったことだけは覚えているから、もうそれで何もかも、どうでもいいと思うことにした。
20170313