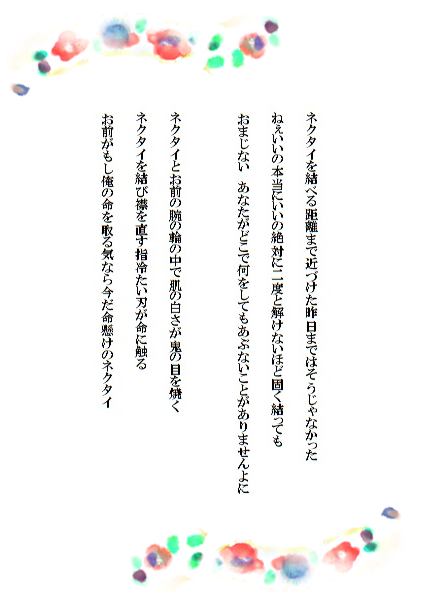
警視庁長官・松平片栗虎から送られてきた小包を開いて、土方は心の底からげんなりした。松平は田舎上がりの芋侍の集団である真選組の直属の上司で、都会の作法に不慣れな自分達の面倒をよく見てくれるのはありがたいのだが、それはときどき押しつけがましいほどお節介なことに思えてならない。鬱陶しいったらない。
「これから、幕府のお偉い方との会談があっから、夕飯いらねぇからな」
土方が台所の奥へ向かって声をかけると、袖をたすき掛けにして前掛けを付けたがひょこりと飛び出してきた。水に濡れた手。何をしていたのか知らないが、前髪がぴょこりと跳ねて遊んでいた。
「はい、分かりました。近藤さんもですよね?」
「沖田もな」
「あら、珍しいですね」
は土方の足元から頭の先まで見上げると、ぱちぱちと瞬きをして唇をきゅっと噛んだ。明らかに、笑いを堪えている顔だった。
「笑いたきゃ笑えよ」
土方はつっけんどんにそう言って、両手をポケットに突っ込む。上等な生地でできたスーツは土方の体にぴたりと合っていて、それは松平がこの日のために仕立てさせたものだった。
今日、土方が会う幕府の偉い方は天人で、地球の古くからの文化にはあまり好意的でない人物らしい。紋付き袴を着て同じ席につくだけで印象を悪くするわけにはいかない。何せ、真選組は荒っぽい浪人の集まりで、ただでさえ心象が悪いのだ。
「よくお似合いですよ」
「着たくて着てるわけじゃねぇよ」
「松平様のお心遣いでしょう」
「俺達のせいで恥かきたくねぇだけだろ」
「皆さんに恥をかいて欲しくないだけかもしれませんよ」
「どうだかな」
は、土方の腕に引っかかった青いものを見やる。
「ネクタイは、締めないんですか?」
「あぁ……」
土方は明後日の方を見やってため息のような声を漏らした。
みっともなくて素直に言う気にはなれなかったが、実はネクタイの結び方が分からなかったのだ。子どもの頃から和服しか着たことがなく、洋服に袖を通したのは真選組の隊服が初めてだったし、ましてやスーツなど見たこともなかった。松平もそのことは分かっていると思うのだが、どうしてかこんなものを送り付けてきて、まったくお節介だったらない。
「あ、土方さん。ここでしたか」
と、どこからか沖田がひょろりと姿を現した。土方と揃いのスーツを着て、やっぱり、ネクタイは締めていなかった。
「おぉ。もうそろそろ出るぞ。支度しとけよ」
「それは分かってるんですけど、これどうやって結んだらいいか分からなくってねぇ」
沖田は片手に握りしめたネクタイを、まるで縄跳びの縄のように振り回しながら言い、その端が危うく土方の目を直撃しそうになる。すんでのところでそれを避けた土方は、殴りかかりそうな勢いで沖田を睨んだが、の笑い声にそれはあっさりかわされてしまった。
「良かったら、結んであげましょうか?」
は前掛けで手を拭うと、沖田が振り回していたネクタイを軽やかにキャッチする。土方と沖田が呆気にとられているのを面白そうに見やって、はにやりと笑った。
「やり方、分かるんですか?」
「えぇ。任せてください」
は沖田の首の後ろに手を回してネクタイをワイシャツの襟の下に潜り込ませると、まるで手品師のような手付きで鮮やかにネクタイを結んでみせた。その手の中で何が起こっているのか、目の前でそれを見ていた沖田にも、真横から見ていた土方にも分からなかった。
きゅ、と静かにネクタイを締めると、沖田は小さく「おぉ」と感嘆する。は最後の仕上げに襟の形を整え、肩にくっついていた埃を払った。
「沖田くんもよくお似合いね」
「ありがとうございます。さんって、何でもできるんですね」
「ふふ、ありがとう」
笑いながら、は何も言わずに土方が持っていたネクタイに手を伸ばす。土方は驚いて息を詰めた。は土方の目を覗き込むと、訳知り顔で目を細めてみせ、それで土方は、が何もかもお見通しであることに気がついた。ネクタイを結べないことを言い出せなくて、沖田にきっかけをもらってラッキーだったと、全て見透かされていることがなんだか悔しい。
は少し背伸びをして、土方の首に両手を回す。たすき掛けにした袖、腕の内側の白さが眩しく目を焼いて、土方は思わず真横に顔をそらした。
「帰りは遅くなりそうですか?」
「あぁ、そうだな……」
土方が歯切れの悪い返事をするので、代わりに沖田が後を継いだ。
「近藤さんと土方さんは松平のおっさんに付き合わされるんじゃないですか? 俺は未成年だからさっさと帰ってきます」
「そう。それじゃお夜食用意しておくわね」
「助かります。あぁいうところで食う飯はどうも口に合わねぇんで」
「偏食も大概にしろよ。ガキじゃねぇんだから」
「マヨネーズばっか啜ってる人に言われたくありませんねぃ」
土方が牙をむく猫のような顔をして沖田を怒鳴るが、の手が土方の頬を優しく叩いてそれを制した。
「じっとしていてくださいな、土方さん」
沖田はしてやったりとばかり、赤い舌を見せると、「先に外に出てます」と捨て台詞を残して台所を出て行った。
「ったく、あの野郎は……」
土方は口の中で汚い言葉を吐いたが、はそれを聞かなかったことにした。
「動かないでくださいって言ってるでしょう」
の指が首筋にあたって、土方はその冷たさにびくりとした。水仕事をしていたせいか、の指先は真っ赤に染まっている。ワイシャツの襟の形を整える指が、土方の首の青く浮き出た血管の上をなぞる。白刃を肌の上に滑られたような鋭さを感じて土方は思わずを睨んだ。は何食わぬ顔をして、土方の喉仏の辺りを見ていた。
「こんなことで目くじら立てていたら、大事な会談もうまくいきませんよ」
「今のは総悟の奴が悪いんだろ」
「土方さんが大人げないんだと思いますけど。沖田くんは甘えてるんですよ、一番隊隊長とは言え、まだ子どもなんですから」
「それが本当ならいつまでもそんなことじゃ困るっつーの」
「それは土方さん次第じゃないんですか?」
「どういう意味だよ」
「それはご自分で考えてくださいな。はい、これでいいですよ」
は最後に肩の辺りを手のひらでさらりと撫ぜ、満足げにうなずいた。土方はきちんと形の整ったネクタイを見下ろして、何も考えずにこれでいいと思うことにし、もう鏡も見なかった。がこれで良いというのだから良いのだろう。
土方は少し迷ったが、今後のためを思い、恥を忍んで口を開いた。
「なぁ。今度、これの結び方教えてくれ」
ところが、はきょとんとした顔をして首を横に振った。
「すいません、それはできないんです」
「何でだよ?」
「だって私、人のネクタイしか結べないんです」
「どういう意味だ?」
「誰かに結んであげることしか、できないんです。自分で自分のネクタイを締める方法は、やったことがないので分かりません」
「あぁ、そうか……」
納得して、土方は静かに肩を落とした。確かに、女が自分の首にネクタイを締める必要などない。やり方を知らなくたって無理のないことだ。
「言ってくだされば、いつでも結びます」
「あぁ、うん、頼む」
力なくそう呟いた土方に、は頼もしく微笑んだ。
20170226