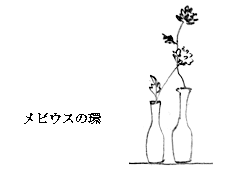
冷えた体を晩酌で温めようと、今夜は母屋で酒宴が催されている。相変わらずのことだけれど、騒がしい夜だ。
宴の中心から抜け出してきた土方は、台所で洗い物をしているの背中を眺めながら、ウィスキーのボトルを開けている。水道の水が流れる音に、氷が鳴る音がかき消されて妙に静かだった。ここまでは隊士達の喧騒も届かない。
の細い背中は少しだけ猫背で、皿を洗ってはすすぎ、湯飲みを洗ってはすすぎ、その作業を黙々と繰り返している。
着物の上からでも分かるその体の線の細さを見て、こいつはいつ飯を食べているのだろう、と考える。隊士達の食事とは時間をずらしているのだろうし、女なのだから、食べる量は少ないのだろうけれど、それをかんがみてもは細い。
無理をしているのではないだろうか。家政婦の仕事は何人か、派遣やパートを雇ってシフトを回しているとはいえ、その中では真撰組結成時からの古株だから責任は重い。今日もこうやって一人で居残って時間外労働をしている。やはり、考えれば考えるほど無理をさせているような気になってくる。
「土方さん、今日はここで飲むんですか?」
土方の視線に気付いたのか、はそう言うと首を巡らせて振り向いた。土方はその目を見つめ返したまま、「そうだな。」と曖昧に相槌を打った。
「そうだなぁって。お疲れなら部屋に戻って休めばいいのに。」
「俺の部屋、西向きだから寒ぃんだよ。」
「暖房入れてきてあげましょうか?」
「まだ飲むからいい。お前も飲むか?」
「私はいいですよ。」
は苦笑いをしながら、土方が持っているグラスにボトルを傾けた。そのまま土方の隣の椅子に腰を落としたので、酌でもするつもりのようだ。
土方はなんとなく面白くなくて、頬杖をついての顔をまじまじと眺めた。には、今何をしてほしいわけでもない。酌をしてもらいたいわけでも、一緒に酒を飲んでほしいわけでもない。この細い体で、そんな無理をしてほしいわけではないのだ。
何となく面白くなかった。
土方はふいに、頬杖をついていない方の手での腕を掴んだ。触れるのでもなく、握るのでもなく、掴んだ。そのやり方に驚いたのか、はきょとんと目を丸くする。
「どうかしました?」
「別に。」
土方は曖昧に語尾を濁しながら、の腕から肩をなぞる。触れてみて初めて分かるその繊細さに、なぜか居たたまれない気持ちになった。
「お前、ほっそいな。ちゃんと食べてんのか?」
「食べてますよ、ちゃんと。」
面白くないのは、がこんなに細くて小さな体で、辛い仕事をなんともない顔でこなして、冷たい水を冷たいとも言わずに毎晩毎晩皿を洗っているからだ。
無理をさせているとは考えたくなかった。けれど、きっとそれが事実だ。
土方はの手を握って、その冷たさに愕然とした。ついさっきまで冷水につかっていた手だ。赤く染まった手の甲と、水仕事で荒れた指先。まるで氷のような手のひらの温度。この手だけで、ウィスキーが冷えるのではないだろうか。
「……寒くないのか?」
思わずそう聞いた。は握られた手のひらと土方の顔を何度か見比べて、にこりと微笑んで見せた。
「土方さんの手があったかいから、平気ですよ。」
「酔っ払ってるからな。」
「……そうですね。酔っ払いですものね。」
土方はの手を離して、その手での首を掴んで引き寄せた。は手どころではなく体中冷えていて、首の裏、うなじの方までひんやりと冷たかった。土方の手が熱いから、余計にそう感じるのだろうけれど、土方は思った。まるで雪そのものみたいだ。
「土方さん、誰か来ちゃうかもしれないですよ?」
「来ねぇよ。」
土方はの首筋に、噛み付くように口付けた。春の雪みたいに冷たいの肌が、酔いに火照った体に心地良かった。脱がせるのが面倒だったから、無理矢理に掛け衿を開いて肌を吸い付かせた。きめ細かい肌の向こうに、細く骨ばった筋肉と骨がある。それは細くて、頼りない。
の体を労わるふりをして、結局乱暴な扱いをしてしまっている自覚はある。無理をさせたくはない、もっと大事にしたい。そう思っているのに、どうしてもうまくいかない。をこんな体にしてしまったのは、自分だ。きっとそうだ。
そうでなければ、この罪悪感の説明がつかない。

私にできることは、もう何もなかった。
くたびれた薄い布団に力なく横たわっている銀時は、体中に包帯を巻いて熱に浮かされている。太刀傷が膿んで発熱しているのだ。日に何度か包帯を変えて、傷口を消毒しなければならず、付きっきりの看病が必要だった。その重労働を私がかって出たのは、他にできることが何もなかったからだ。それくらいのことしかできなかったからだ。
「だいぶ良くなってきたんじゃない?」
布団の上で半身を起こしている銀時の体を拭いてやりながら、その背中に問いかけた。銀時は「あぁ」か「おう」か、どちらともつかない相づちを打つ。
包帯をほどいた体に残る赤黒く変色した傷口は、これでも見るに耐えるほどにはましになってきたのだ。銀時の体は、布巾ごしに触れても熱い。
「悪ぃな、こんなことまでやらせちまって。」
「頼んできたのは銀さんの方でしょ。今更じゃない。」
「お前以外の奴に頼んだらそれこそ絶体絶命だったんだよ。知ってんだろ? お妙とかお妙とかお妙とか。」
「それ、お妙さんに伝えておいてもいい?」
「やめろ、殺す気か。」
小さな嘘や冗談は、ころころと転がるように軽やかだ。まるで赤ん坊をあやすおもちゃみたいだと、いつも思う。
今この瞬間の涙を止めるための玩具は、数年もすれば忘れ去られて何の役にも立たない。こんな刹那的なものでは、銀時を救えない。
「もう少ししたらお風呂にも入れるから、もう少しの辛抱ね。」
「そんなのは別に平気なんだけどな。」
銀時の筋肉質で重い腕を持ち上げて、汗を拭う。何となく銀時の目を直視できなくて、まだ抜糸を済ませていない生々しい胸の傷をじっと見ていた。
「……悪かったな。」
「今更だって言ってるでしょ。」
「そうじゃねぇよ。」
ふいに、銀時の声が強くなる。触れていた腕の皮膚の下で、筋肉が強張ったと思ったら、銀時の手のひらが固く結ばれていた。手の甲に浮き出た血管を見下ろしながら、息を飲む。銀時の呼吸の音が聞こえなかった。
「そうじゃないって、何が?」
銀時は答えない。歯ぎしりみたいな、ぎしぎしした嫌な音が聞こえるような気がした。きっと銀時にも聞こえているだろう、これは、私たちの心が軋む音だ。
「……なぁ、。」
「なに?」
「……しんどい。」
いつもの、投げやりな物言いとは違って、その絞り出したような声は頼りなく切実だった。思わず見上げると、銀時は眉間に深い皺を刻んで歯を食いしばっていた。
「銀さん。」
「……しんどい。」
同じ言葉を二度繰り返して、銀時は何かを堪えるようにぐっと俯いてしまう。力のやり場がなく、握った拳が震えていた。
傷もようやく治りかけているというのに、こんなに興奮してしまっては体に毒だ。どうにかしてやらなくては、と考える。けれど、何も浮かんでこなかった。
こんな時、いつも思う。私がこの人の恋人だったら良かったのに。
「……銀さん。」
もしもの話を精一杯の気持ちで振り切って、銀時の拳を両手で包み込んだ。銀時はその手のひらを握り返しての手を掴むと、指が潰れそうになるほど強く握り締めた。銀時が一つ、呼吸をする。泣きそうに熱い息だった。
「銀さん。」
「……なぁ、」
「うん。」
「ちょっと、肩貸してくれ。」
銀時は言うなり、倒れこむようにして私の肩に頬をうずめた。手を握っているだけでは支えきれなくて、もう片方の手を背中に回して抱きしめる。包帯を巻いていない、抜糸も済んでいない銀時の素肌はでこぼこで熱かった。
「……銀さん。」
「悪かったな。」
「何が?」
「……また、喧嘩した。」
銀時の手は、私の手を離れることもなく、私の体に触れることもなく、銀時の中に淀む怒りとか悲しみとか、そんな言葉では表しきれない感情をただ堪えるためだけに結ばれている。
その強張った体をほぐしてやりたくて、子どもをあやすように銀時の背中を撫でた。銀時は子どものように、手のひらの動きに合わせて浅く呼吸をしている。
「そんなの、いつものことでしょ? 大丈夫よ。」
「そうじゃねぇんだって。」
銀時は一言強い口調で否定すると、それきり黙りこんでしまった。結局銀時は我慢をするばかりで、私を受け皿に吐き出そうとはしてくれなかった。
想像するに、銀時は昔のことを物語にして口に乗せることを怖がっているのだと思う。明確な理由がある訳ではなく、本能的に恐れているのだろう。そこへ高杉や桂が昔の傷を抉るようなことをするから、こうやって銀時が傷付く。
二人を責めるつもりはないし、誰に罪があるわけでもない。そんなことは分かっている。強いて言うならば、銀時が傷付いたままそれに耐え続けなければならないのは、それを救う術を未だに見つけられないことが原因だ。
「……銀さん、ごめんね。」
「何が?」
「……何にもできなくて。」
もしも私が銀時の恋人だったら、してあげられることがあったかもしれない。
もし望まれるならば、銀時を抱いてあげることも、抱かれてあげることもできる。私が銀時の恋人だったら、そうやって銀時を救う手立てだって可能性の中にはあったはずだ。けれどそれを本気で望むなら、銀時と出会ったあの寺子屋からやり直さなければならない。もしもの話は、時に絶望的に残酷だ。
「……私に、できることがあったらよかったのに。」
無力な両手で、必死に銀時を抱きしめた。銀時の抱えているもの全てを受け止めてやりたくて、ほとんど祈るような気持ちで指先にまで力を込めた。
ふいに、銀時は身動ぎをして、から手を離した。顔は俯いたまま、耳元に唇を寄せてくる。何かを言おうとしているようで、そこに意識を集中させると、吐息だけの声が聞こえた。
「……いてくれるだけでいいよ。」
「……銀さん。」
「いいんだよ、お前はそれで。」
言うなり、銀時は再び私の肩に額を押し付けてじっと黙り込んでしまった。
銀時が手のひらの中からするりと抜け出してしまったような気がした。唐突に空しくなる。いるだけでいいだなんて、そんなことを言われるぐらいなら、無理矢理に脚を開かされる方がまだましだ。その方がまだ、役割がある。
どうして私は大切なこの人のために、身を削ることができないのだろう。この無力感はどうやったら埋められるのだろう。
分からなくて、どうしても分からなくて、結局何もできないまま夜は更けていく。

久しぶりの仕事の後、給料が入った茶封筒をそのまま財布がわりにして大好きな甘味に舌鼓を打っていると、偶然にと遭遇してしまった。
遭遇と言っても、道の向こう側にその姿を認めただけで、しまったと言うのも、の隣に大嫌いなマヨラーの姿をも認めてしまったからだ。
と野郎は二人並んで店の主と話をしているようだけれど、そこが何の店なのかは遠目には分からない。の顔を見たら挨拶くらいはしたいのに、あの野郎とは顔を合わせただけで喧嘩になってしまいそうで、わざわざこちらから声をかけるのはあまりに億劫だ。さて、どうしたものか。
と野郎は二人で店の主と話をしているようだけれど、そこが何の店なのかは遠目には分からない。おそらくは真撰組の屯所で使う何かの買い出しだろう。
けれど、二人が仲睦まじく笑顔を交わしている姿を見ると、なんだか無性に腹立たしかった。理由は分からない。前の日の酒がまだ体の中に残っているように、じわりと重く、いらついた。
みたらし団子を齧りながら得体の知れない怒りと格闘していると、ふいに野郎だけが踵を返したのが見えた。やばい見つかるかなと思うのと同時に目があってしまう。土方十四郎は目尻をぴくりと痙攣させて、あからさまに嫌悪感を示した。まるで鏡を見ているような気がした。銀時もあからさまな嫌悪感を放出していたから。
「なんだ、てめぇか。」
「それはこっちのせりふだよ。」
「昼間っから茶屋とはいいご身分だな。」
「そっちこそ公務員のくせに昼間っからデートかよ。」
そう言うと、土方は意外そうにばちくりとまばたきをした。「見てたのかよ。」と、一言言うと、店先でまだ店主と話し込んでいるの方を振り返る。
「別にそんなんじゃねぇよ。ただの買い出しだ。」
「真撰組の鬼副長自らが?」
「人手が足りてねぇんだよ。それに、今日は胴着やら竹刀やらの仕入れも兼ねてんだ。あいつだけに任せられねぇだろ。」
銀時は無性に苛々していた。土方がに向けている眼差しは傍目から見て明らかなほど穏やかだった。さっきまで眉間に深く刻まれていた皺もほどけている。こいつと顔を合わせれば間違いなく喧嘩になるはずだと思っていたのに、この腑抜けた面は何だ、腹立たしい。
「それはそれは、お熱いことで。」
「だから違うって言ってんだろ。」
「あぁそうなの? それに言ったらどんな顔するかね?」
「うるせぇっつってんだよ、黙れ。」
その声にも、心なしか覇気が感じられなかった。銀時はからかってやるのも馬鹿らしくなって、手遊びに咥えていた団子の串をばきんと折った。
小気味いい音が、耳の奥に余韻を残す。じわりと、怒りを沈める鎮静薬みたいに。
どうしてこんなに腹が立つんだろう。土方がに惚れていることくらい、分かっていたことだ。二人が一緒にいるところを見るくらい、どうということでもないだろう、どうしたっていうんだ、一体。
「この間、」
ふと、土方が口を開いた。少し言い淀む間があって、銀時はここぞとばかりに口を挟む。
「何だよ?」
「いや、この間がお前ん家行っただろ。」
「来たよ。それがどうした?」
さらにたたみ掛けると、土方は口元を引き結んで黙り込んでしまった。が自分以外の男の家に上がり込んでいることが気にくわないのだろうか、常識的に考えればそうだろう。
けれど、土方はこう言った。
「何か、あったのか? お前等」
予想外の問いかけを聞いて、銀時は目をぱちくりと瞬かせた。土方は気まずそうに目を泳がせている。まるで、初めて恋を知ってしまった子供のような顔だった。
きっと内心は羞恥心に悶えていることだろう。そんな自分勝手な葛藤に付き合ってやる義理もないので、銀時は茶を啜りながら質問の答えを模索した。
何かあったのか、と聞かれれば、あった。怪我の看病をしてもらって、その上、どうしようもなくやり場のない猜疑心や喪失感の処理に付き合わせてしまった。今までにもこういうことはままあって、その度には辛抱強く側にいてくれた。銀時にとっては、血で汚れた薄汚い過去を知る数少ない人間の一人で、だからこそ誰にも言えない言葉を吐き出せる。
が自分の側にいてくれることは、わざわざ感謝をするような特別なことではなくて、もっと自然な当たり前のことだと思っている。昼と夜が巡りめぐるように、四季が移ろいゆくように、それくらい当然のことだった。考えるよりも先にそう感じている。
あぁ、そうだ。唐突に思い至った。
つまり、土方に嫉妬しているのだ。当たり前の恋人同士のように、と並んで歩くことができる土方に、嫉妬しているのだ。
当たり前に一緒にいたが、まるで知らない女になってしまったようで、自分は寂しがっていたのだ。きっとは銀時が望めば肩でも、膝でも、おそらくは体すら預けてくれるだろう。けれどそれはもしもの話だ。現実にはありえない。そうやってを繋ぎとめる手段を持っているのは、土方なのだ。
「別に、何もねぇよ。」
そんなことを感じてしまった自分が悔しくて、ぶっきらぼうに嘘を吐いた。そもそも大嫌いなこいつに本当のことを話してやる義理なんかないのだ。
土方はそれ以上追求はせず、曖昧に相槌を打っただけで黙り込んだ。
本当は、自分で思うよりもずっとに依存しているのだと思う。そう考えなければ、土方に嫉妬する理由も説明がつかないし、事が起こるたびにに甘えてしまう自分の情けなさにも言い訳ができない。
溜息がこぼれた。

20100517