時には昔の話を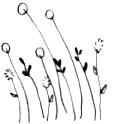
河川敷に、子供たちの楽しげな笑い声が響いている。
定春の周りに群れるように集まった子ども達が、その毛並みを撫でたり引っ張ったり、その背中に乗って遊んだり、まるで移動遊園地の一角でも見ているようだ。それを先導しているのは神楽で、ガキ大将みたいに声を張り上げながら皆で大騒ぎしている。定春の背中から転げ落ちそうになった子どもを新八が受け止めたかと思うと、その頭を定春ががぶりと噛んでどっと笑いが起きた。その拍子に子どもがひとり川の中に落ちて派手な水しぶきが上がる。
「みんな、楽しそうね」
ベンチに座ってほがらかに微笑みながら、が言った。
「ガキは呑気でいいよなァ」
その隣で、チュッパチャップスを舐めながら銀時がごちた。二人の間には大きなバスケットがあって、中にはサンドウィッチやフルーツ、ジュースやお菓子がたっぷり入っている。
の知り合いのペットが行方不明になったときに、が万事屋を紹介して無事にペットが戻ってきた、ということがあって、今日はそのお礼にが3人をもてなそうということになった。それにくっついてきた子ども達は神楽がよく一緒に遊んでいるよっちゃん達で、ごちそうの匂いにつられて着いてきたらしい。
気持ちのいい昼下がりだ。優しい風が吹いていて、小鳥がさえずる声が聞こえていた。
「銀さんだって十分呑気じゃない」
「呑気じゃねぇよ。これは瞑想してんの。宇宙の真理に思いを馳せてんだよ」
「あぁ、そう。それじゃ、どうして流れ星に3回願いをかけたら叶うのか、分かったら教えてね」
「……お前、なんか俺のこと馬鹿にしてない?」
「まさか。銀さんのそういうところ、わたし大好きよ」
「やっぱ馬鹿にしてんじゃねぇかっ」
銀時は吐き捨てるようにけっと毒づいて、ベンチに仰け反った。癖の強い天然パーマが風にふわふわ揺れていて、動物の毛並みのようだ。
はバスケットの中から大きなポットを取り出して、紙コップ2つに温かいお茶を注ぐ。ひとつは銀時の膝のそばに置いて、もうひとつは自分で口をつけた。
「ねぇ、銀さん。なんだか昔のこと思い出さない?」
「あぁ? 何を?」
「昔、たまにみんなでこんな風にピクニックに行ったじゃない。寺子屋の近くに川原があって、先生と私とでお弁当作って」
「あぁ、そう言えばそんなことしたな」
「みんなふんどし一枚で川遊びしてて、気持ちよさそうで羨ましかったなぁ」
「何言ってんだよ。お前も結局着物のままで川ん中突き落とされてたじゃねぇか」
「あぁ、あったあった。高杉くんが桂くんに怒鳴り散らされてたっけねぇ。元気にしてるかなぁ、みんな」
思い出し笑いをしてくすくす笑うを横目に、銀時は複雑な面持ちで茶をひとくち口に含む。
「あいつらがそう簡単に死ぬかよ」
「生き死にの話じゃなくって。健康で元気に過ごしてるかなって話よ。銀さんは桂くんとたまに会ってるんでしょ? どんな様子なの?」
「あいつは相変わらず馬鹿やってるよ。馬鹿なんだから、元気だろ」
「じゃぁ、高杉くんはどうかな?」
「あいつはいつも元気じゃねぇし。……っていうか、元気な高杉ってなんだよ? 想像しただけでも気持ち悪ぃわ」
「うぅん、それもそうねぇ……」
はつい、銀時が言うところの「元気な高杉」を想像してしまって、表情を強ばらせた。想像してはいけないものを想像してしまったような気がして、わけもなく何かに謝りたいような気分になる。
しばらく子ども達の笑い声がこだました。先に口を開いたのはだった。
「銀さんは、高杉くんに会いたいって、思ったりしないの?」
は純粋な眼差しで問い掛ける。銀時は子ども達を見守りながら、高杉と最後に会った時のことを思い出していた。
「そうだなァ。次に会った時はぶった斬るとか言っちまったから、会いたくはねぇかもな」
「桂くんも?」
「言ってた言ってた。あいつなら絶対やるね。間違いなく」
「そんなに喧嘩ばっかりしなくてもいいじゃないって、私なんかは思うんだけど。そうもいかないのね、きっと」
「そうだなぁ」
ひと時、強い風が吹いた。川面が音を立ててざわめいて、子ども達が大声を上げてむやみやたらに風に逆らって大声を上げている。は長い髪を手で抑えて、バスケットが倒れないよう、片手でそれを抱え込んだ。
銀時はその横顔を眺めて、物思う。
にとっては、楽しい子ども時代の思い出なのだろう。けれど、銀時にとってそれは因縁だ。桂、高杉、攘夷戦争の後再会したふたりとは、子どもの頃のままの気持ちで顔を合わせることは、もうできない。仕方のないことではあるし、もうとっくの昔に諦めてしまったことだ。けれどがまだこんな風に笑うから、いたたまれない気持ちになった。
「ごめんな」
「え?」
「俺達、いっつも喧嘩ばっかして」
の丸い目が銀時を射た。まるで子どものように純粋な眼差しに、銀時も子どもの頃に戻ったような錯覚に陥って目の前がくらくらした。
子どもの頃も喧嘩ばかりしていたし、今も顔を合わせれば口喧嘩ばかり。これから先は、剣さえ抜いて戦うこともあるだろう。きっとその運命からはもう逃れられない。その度に、きっと何度でも、を傷つけるのだろう。
そんな銀時の思いを裏切って、はにこりと微笑んだ。
「いつか、皆でゆっくり話ができる時が来るといいね」
の言葉に、銀時はぱちくりと瞬きをした。その銀時の顔がなんだか情けなくて、は思わず吹き出した。
「皆、今より大人になったら、きっと話くらいはちゃんとできるよ。そうしたら、子どもの頃みたいに、みんなでピクニックしよう」
はどこまで本気なのだろう。銀時は思う。
きっとの望みは叶わない。桂とともに船の上で対峙した高杉の顔を思い浮かべると、この面子が同じ場面に居合わせることを想像したらそこには死臭が漂うような気さえする。の夢をぶち壊すのはきっと自分だ。そう思うと吐き気がした。
それでも今、は隣にいて、夢のような未来に思いを馳せて、まるでそれが現実に見えているかのように幸せそうに笑う。ただそれだけが、銀時にとって救いだった。
「……そうだな」
銀時はそう言って、悲しげに微笑んだ。
その笑顔の意味を、もよく分かっていた。
20140922
どんなに大人になって変わってしまっても、昔も今も、みんなが大好き。